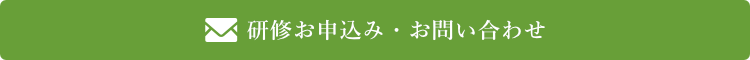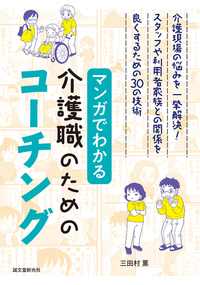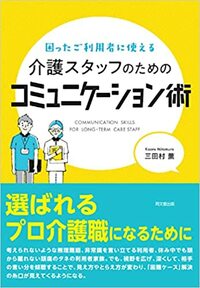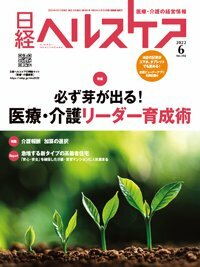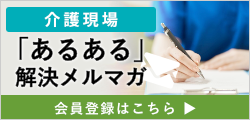訪問型・施設型・デイサービスなどの介護事業所の職員を研修し
離職予防・営業力強化・チームワーク向上・リーダー育成・ブランド事業所づくりをサポートします。
離職予防・営業力強化・チームワーク向上・リーダー育成・ブランド事業所づくりをサポートします。
- ホーム
- 三田村薫の「介護のアレコレ」ブログ
三田村薫の「介護のアレコレ」ブログ
怒り
2022/03/23『怒り』について考えてみました。
●家族に対する怒り
● 上司に対する怒り
● 友人に対する怒り
● 顧客に対する怒り
● 自分に対する怒り
クライアントさんが『怒り』について話されるときは、『怒り』を否定的に話されます。
当たり前ですが、誰でも怒りが喚起されるような事があったら、嫌だし、不快だし、否定しますよね。
心理学では、怒りは第二次感情といわれます。怒りの前には、辛い、悲しい、苦しい、さみしい、不安などの感情があって、次に『怒り』というフレームになっていると考えます。
先日、友人が「テニスで上手く打てなかったら、『やってやる!』ってなるんだよね」と話してくれました。友人のように「やってやる」と怒りを活用できる人と怒りを感じて恐怖に押しつぶされる人の違いを考えてみると、『怒り』を原動力にして、いつも以上の成果を出せた経験は誰にでもあるのではないかと。
怒りを感じて目の前の人に暴言を吐いたり、暴力をふるったりしたら問題ですが、「やってやる」と自分を成長させるエネルギーに変えることができれば、怒りはプラスに働きます。
でも、一般的に「怒り」の感情は、否定的に扱われ、抑圧されて、大人になればなるほど、素直に感情表現することを善とせず、冷静であること、控えめであること、慎重であることが美徳とされます。
怒りを露わにすることは「みっともない」ということが浸透しているため、怒りはダメなもの、あってはいけないものと過度に否定している人が多いのではないかと。
でも、怒りがない人なんていません。あるものを「ある」と認めるだけで、随分と生き方は変わるのではないでしょうか。
もし、身のまわりの現実に失望や退屈さを感じているのなら、それは「楽しい」や「面白い」が欠けているのではなく、「怒り」が欠けているのかも。
感情は「喜怒哀楽」のどれか一つだけを抑え込むことはできません。喜びを抑圧すれば、その分だけ他の感情も薄まります。それと同じように怒りを抑圧すれば、その分だけ他の感情も薄まります。
台風は温帯低気圧に変わってもエネルギーの大きさは変わらないように、『怒り』の名称(フレーム)は変わっても、自分を成長させるエネルギーとして活用できるはずです。
自分にある『怒り』を受け入れているからこそ、プラスに活用できます。
何かにイラッとしたとき、内面にある『怒り』を「あるある」と見つめるところからなのではないでしょうか。
■お申込受付中
このたび、同文館出版様から『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』を刊行させて頂くこととなりました。4月8日発売です!
『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』出版記念講演会
●講演日:2022年 4月13日(水)
●時間:16時半〜18時
●形式:オンライン(Zoomを使用します)
●講演者:三田村薫(コミュニケーションオフィス3SunCreate代表)
●詳細・お申込みはこちらからお願い致します。自己理解と他者理解
2022/03/18●自己理解は、他者理解に通じる
●苦手な相手を受け入れるためには、自己理解から
●自分が変わるから、まわりの人が変わる
これらのことは、私自身もセミナーで話しますし、とても本質的なことだと思います。
ですが、『自己理解』という言葉のイメージ(フレーム)の違いで、“自己理解=他者理解”という捉え方が変わるのではないかと思うのです。
「自己理解が進むことで、まわりの人が変わっていく」と言われたとき、私がもった最初のイメージは、内省を深めていくと、直接的に関わらなくてもまわりの人が変わっていくといったものでした。
今から考えると極端なイメージですが、このイメージも、ある位置からみると「そうだな」でもあり、ある位置からみると「そうじゃない」となるのではないかと。
「そうだな」の位置からみると、私たちは、出来事や人や言葉に伴ったイメージによって、自分が良い・悪いと反応している、全てが内面世界で起こっていること。外界からの刺激(出来事・人・言葉など)によって、内的イメージ(フレーム)が発動されて、良い・悪いと自分の内面が反応をしている。ということは、内的イメージが変わると外界が変わるという捉え方。
「そうじゃない」の位置からみると、『自己理解』とは、内省して「そういうことだったんだ」という理解をもとに、他者に関わっていくこと。そして、その関わりのなかで生じる葛藤を素材にして、更に内省を深めていく。そして、更に自己理解をベースに他者と関わり、そのことで生じるトライアンドエラーで内省を深めていくことを『自己理解』という捉え方。
「正しいvs間違っている」と考えると、この2つにわけることができます。ですが、この二元論ではなく、この両方の考えが必要なのではないでしょうか。
たとえば、上司から、「ホント、つかえない奴だな!」と辛辣なことを言われたとします。こんな言葉を発する上司のことは、許せないと嫌悪するのは当然だと思いますが、この出来事を自己理解に繋げて考えていくと、辛辣なことを言われたときの自分の内面の反応を捉えて、どんな感情・感覚があるのかを観察する。そして、その感情・感覚の土台となっている思いを理解すること。
この場合、上司から辛辣なことを言われて落ち込んだとします。ネガティブな感情・感覚の土台となっている思いが『劣等感』だったとすると、内面に『劣等感』があるから、「つかえない奴」と劣等感を触発されるようなことを言われて反応した。
わかりやすいように極端に考えると、「私は有能」と自信のある人は、上司から「つかえない奴」と言われても、「あの上司は見る目がない」と意に返さないはずです。
更に自己理解が進むと、「つかえない奴だ」と言ってしまう上司には、どんな思いが根底にあるのか?と考えると、相手を抑え込む(抑え込んで自分の有能性を示す)手段として辛辣なことを言っていると考えると、同じ劣等感があるのではないかと推察することができます。
「私は有能」と自信のある人は、わざわざ辛辣なことを言って相手を抑え込むなんてしません。
こうして、辛辣なことを言う上司のことを理解できると、嫌悪が好感にまで変化しないにしても、以前よりは肯定できるようになるのではないでしょうか。肯定しているということは、差ほど意識しなくても自然に接することができます。すると、自分の言動が変わるから、相手の言動が変わる、相手が変わったようにみえる。
これが「そうだな」の位置からみた、自己理解=他者理解。
「そうじゃない」の位置からみると、「つかえない奴だ」と言ってしまう上司には、同じ劣等感があるのではないかと理解して、以前より肯定できるようになる。
そして以前より、自然に接することができるようになって、暫くは平穏に過ごせるようになる。でも、忘れた頃にまた何かミスをして上司に傷つけられたりすると、「理解したはずなのに…何がダメなんだよ!」と落ち込む。そして、また同じプロセスを辿り、更に理解を深めていく。そして、諦めずに自分の内面と上司と向き合っていく。このトライアンドエラーを繰り返していくことで、上司に対する見方も自分の内面世界の理解も深まっていく。自己理解と他者理解が進む。
これが「そうじゃない」の位置からみた、自己理解=他者理解。
自分を傷つけた人のことを受け入れて、自ら関わっていくということは、膨大なエネルギーをつかいます。一度でも、勇気を出してイヤな上司とコミュニケーションとったのに何も変化しなければ、「何も変わらないじゃないか!精神世界を学んでも無駄なんだ!」となるのは、よくわかります。
ですが、「良いvs悪い」「正しいvs間違っている」「好きvs嫌い」の二元論では、何も変わらないのではないでしょうか。
一方だけでは明確にならないことも、多方からみると明確に捉えることができる。角度を変えてみることで立体的に物事を捉えることができます。
多元的に広い視野で物事を捉えることができれば、きっと見ている世界は変わるはず。
「そうだな」も「そうじゃない」も、また「そうだなandそうじゃない」も全てが“自己理解=他者理解”には、不可欠な素材なのではないでしょうか。
*******
■お申込受付中
このたび、同文館出版様から『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』を刊行させて頂くこととなりました。4月8日発売です!
『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』出版記念講演会
●講演日:2022年 4月13日(水)
●時間:16時半〜18時
●形式:オンライン(Zoomを使用します)
●講演者:三田村薫(コミュニケーションオフィス3SunCreate代表)
●詳細・お申込みはこちらからお願い致します。関連エントリー
-
 「介護スタッフのためのハラスメント対策研修」の受講感想の一部をご紹介します
■介護スタッフのためのハラスメント対策研修講師:三田村薫実施日:2022年7月27日 13:00~15:30開
「介護スタッフのためのハラスメント対策研修」の受講感想の一部をご紹介します
■介護スタッフのためのハラスメント対策研修講師:三田村薫実施日:2022年7月27日 13:00~15:30開
-
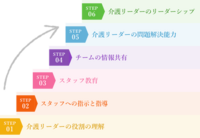 出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。
先日開催しました出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。
出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。
先日開催しました出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。
-
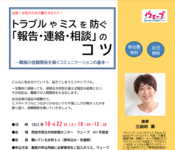 「出張!女性のための働き方セミナー」アンケートの一部をご紹介します!
出張!女性のための働き方セミナー アンケートトラブルやミスを防ぐ「報告・連絡・相談」のコツ~職場の信頼関係を築
「出張!女性のための働き方セミナー」アンケートの一部をご紹介します!
出張!女性のための働き方セミナー アンケートトラブルやミスを防ぐ「報告・連絡・相談」のコツ~職場の信頼関係を築
-
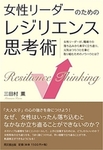 『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します!
先日、オンライン開催しました『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します。当日は、
『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します!
先日、オンライン開催しました『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します。当日は、
-
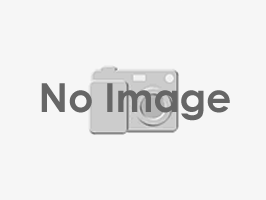 『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介します!
先日、オンライン開催しました『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介し
『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介します!
先日、オンライン開催しました『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介し

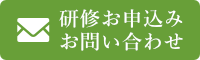
 事業所を良くしたい、経営者様、責任者様、一度お話をお聞かせください!
事業所を良くしたい、経営者様、責任者様、一度お話をお聞かせください!