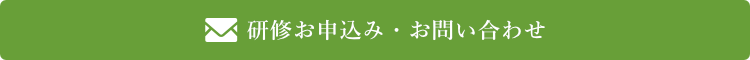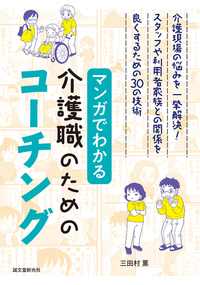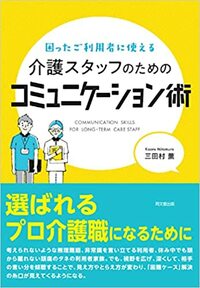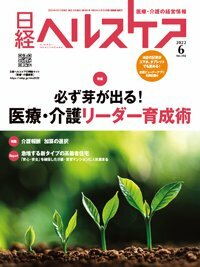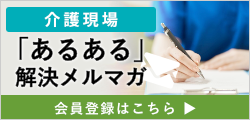訪問型・施設型・デイサービスなどの介護事業所の職員を研修し
離職予防・営業力強化・チームワーク向上・リーダー育成・ブランド事業所づくりをサポートします。
離職予防・営業力強化・チームワーク向上・リーダー育成・ブランド事業所づくりをサポートします。
- ホーム
- 三田村薫の「介護のアレコレ」ブログ
三田村薫の「介護のアレコレ」ブログ
自分に誠実に生きる
2022/04/02友人とカフェに入ったとき、隣の席のグループが騒がしくて「席をかえてもらおうか?」と話していると、別のお客さんが「ちょっと!迷惑を考えてよ!」と強く注意するという場面に出くわしました。
突如、隣の席で起こったことに私たちの会話も一時中断。
一瞬、店内にも緊張感が走りました。
店員さんが間に入って、何事もなかったように元通りの空気感になったのですが、友人は会話の続きを話しながらも、小声で「心が辛い」と。
私はというと、「何が?」という感じ。
そこで思ったのですが、
●怒りを露わにしている人を目の当たりにすると影響を受けるタイプ
●怒りを抑圧している人を目の当たりにすると影響を受けるタイプ
2つのパターンだけではないと思うけど、人によって影響を受けやすいパターンがあるのではないかと。
私はどちらかというと後者。
影響を受ける(反応する)ということは、自分の内面にある否定していることと考えると、
●怒りを露わにしている人に反応する→怒り(感情)を表現してはいけない
●怒りを抑圧している人に反応する→怒り(感情)は素直に表現するべき
この両者に共通しているのは、『誠実に生きる』ということなのかも。
コーチがクライアントにフィードバックするとき、「傷つかないように伝えなきゃいけない」と考えて言葉を選んで伝えるのか、「多少は傷つけるかもしれないけど、ありのまま伝える」ことがコーチとしての誠実さだと考えるのかと似ているように思う。
●自分の言動で相手を傷つけてはいけないという誠実さ。
●自分が悪者になっても相手の成長を信じる誠実さ。
傷つくことに価値を見出しているかでも、捉え方は違ってくるはず。
これは、『誠実に生きる』という捉え方の違いでもあると思う。
確かに、人が学ぶときや成長するときは、傷ついたとき(ショック、挫折、失敗など)に立ち止まることで、慣れ親しんだ思考や行動ではない新しい発想で一歩進めるのかも。
でも、傷つくこと(ショック、挫折、失敗など)で成長できるという考えが極端になって、傍若無人に振舞うというのも違うし、極端に傷つくこと(ショック、挫折、失敗など)を避けたいと、自分の内面にある怒り(感情)をナイものとして抑圧するのも違う。
どちらが正しい・間違っているということではなく、この両方が認識できている状態が『誠実に生きる』ことに繋がるように思う。
両方が認識できて、初めて選択肢がうまれて、意識的に選択できる。
無意識的な反応は、選択肢がない自動反応。
この自動反応を長年続けていると、だんだん「怒り(感情)をぶつけてはいけない」が極端になって、自分の内面にある怒り(感情)を抑え込むことになるか、「ありのままを伝えるべき」と言葉を選ばずにズケズケ言ってしまうことになる。
人は、無意識的に極端になりやすい。
意識的に生きることが『誠実に生きる』と考えると、適切に傷つくこと(ショック、挫折、失敗など)で意識的に立ち止まることができる。そして、自分が影響を受けるパターンが起こったとき、意識的に「影響を受けない」と選択することはできるはず。
■お申込受付中
このたび、同文館出版様から『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』を刊行させて頂くこととなりました。4月8日発売です!
『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』出版記念講演会
●講演日:2022年 4月13日(水)
●時間:16時半〜18時
●形式:オンライン(Zoomを使用します)
●講演者:三田村薫(コミュニケーションオフィス3SunCreate代表)
●詳細・お申込みはこちらからお願い致します。関連エントリー
-
 「介護スタッフのためのハラスメント対策研修」の受講感想の一部をご紹介します
■介護スタッフのためのハラスメント対策研修講師:三田村薫実施日:2022年7月27日 13:00~15:30開
「介護スタッフのためのハラスメント対策研修」の受講感想の一部をご紹介します
■介護スタッフのためのハラスメント対策研修講師:三田村薫実施日:2022年7月27日 13:00~15:30開
-
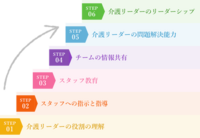 出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。
先日開催しました出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。
出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。
先日開催しました出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。
-
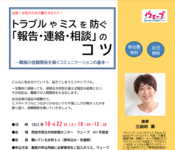 「出張!女性のための働き方セミナー」アンケートの一部をご紹介します!
出張!女性のための働き方セミナー アンケートトラブルやミスを防ぐ「報告・連絡・相談」のコツ~職場の信頼関係を築
「出張!女性のための働き方セミナー」アンケートの一部をご紹介します!
出張!女性のための働き方セミナー アンケートトラブルやミスを防ぐ「報告・連絡・相談」のコツ~職場の信頼関係を築
-
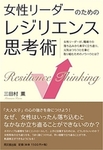 『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します!
先日、オンライン開催しました『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します。当日は、
『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します!
先日、オンライン開催しました『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します。当日は、
-
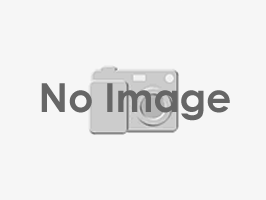 『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介します!
先日、オンライン開催しました『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介し
『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介します!
先日、オンライン開催しました『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介し

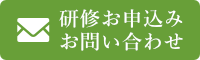
 事業所を良くしたい、経営者様、責任者様、一度お話をお聞かせください!
事業所を良くしたい、経営者様、責任者様、一度お話をお聞かせください!